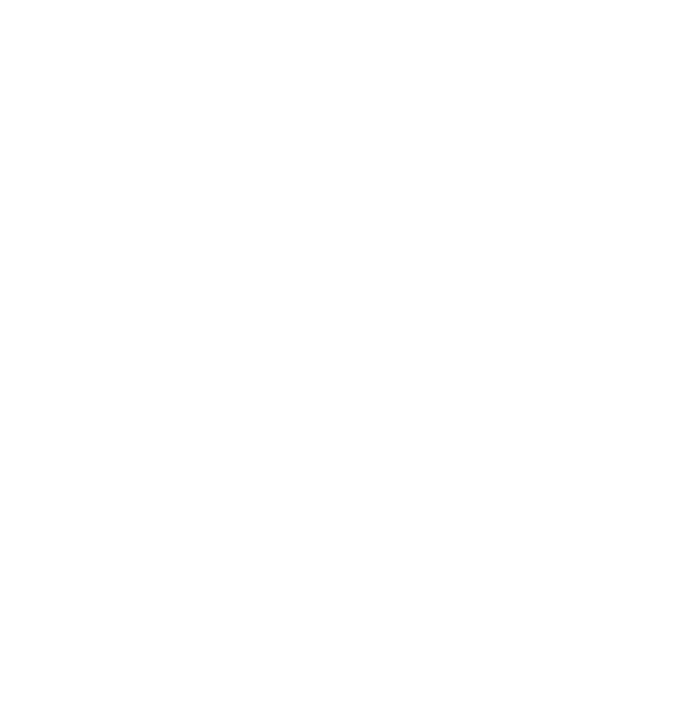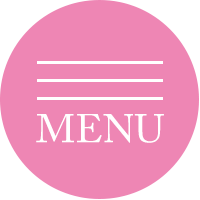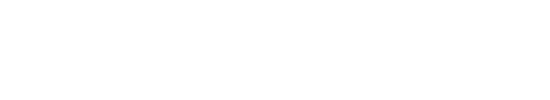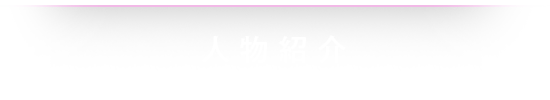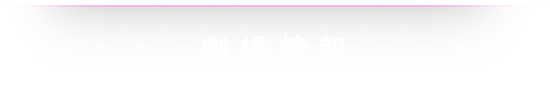イランが目指す「理想のイスラム国家」の陰で、少女たちは貧困にあえぎ、強姦され、殴られ、自傷し、体を売り、逮捕されている。政府も家族も彼女らを救うのではなく、抑圧してなきものとする。本作は、少女更生施設に響く慟哭を映し出すことで国民の真実を暴く、静かでありながら、強い怒りに満ちたドキュメンタリーだ。
石井 光太
作家
社会や家族の矛盾は最終的に少女たちを犠牲にすることがみごとに描かれている。
そんな光景が今の日本と重なって見えるのは私だけだろうか。
そんな光景が今の日本と重なって見えるのは私だけだろうか。
信田 さよ子
原宿カウンセリングセンター所長
「夢は死ぬこと」少女は穏やかに呟いた。叔父から受けた性暴力を母は信じてくれなかった。どこかでみたことのある表情があった。あなたの隣にもいるかもしれないその瞳。罪を犯した少女たちは誰もがSOSを送る被害者だった。
ある少女は出所するその日、夜明けまで眠れずにいた。月明かりの中「社会には勝てないのだ」と塀の外の世界への恐怖を打ち明ける。彼女たちは時に歌い、泣き、お互いの痛みを抱きしめる。そんな居場所がそこにはあった。「おかえり」と抱きしめてくれる家族がいると知った時、「夢は生きること」になった彼女の笑顔を忘れてはいけない。
ある少女は出所するその日、夜明けまで眠れずにいた。月明かりの中「社会には勝てないのだ」と塀の外の世界への恐怖を打ち明ける。彼女たちは時に歌い、泣き、お互いの痛みを抱きしめる。そんな居場所がそこにはあった。「おかえり」と抱きしめてくれる家族がいると知った時、「夢は生きること」になった彼女の笑顔を忘れてはいけない。
伊藤 詩織
ジャーナリスト・ドキュメンタリー監督
窃盗、薬物、殺人…私たちはそれを、咎められるだろうか。それが、裏切られ続けた彼女たちの、最後の居場所だとしたら。「帰りたい?」「家出をしてはだめだよ?」「家族なんだろ?」“更生”すべきものがあるとすれば、大人たちの空虚な言葉だろう。
安田 菜津紀
フォトジャーナリスト
誰にも助けてもらえない「ISOLATE(孤独)」な状態が、少女たちを犯罪に追い詰めている。世界中、きっとどこでも同じだ。犯罪の陰には悲しみがある。そのことを知ってほしい。
寮 美千子
作家・奈良少年刑務所元講師
「罪を犯してはいけない」「人を殺してはいけない」今まで言えていた言葉が言えなくなった。彼女たちの生の前には、倫理など薄ら寒い綺麗事でしかない。生とはこんなに苦しいものだったのか。バレーボールをし、絨毯を洗う少女達の笑顔は、私達と何も変わらないのに。施設で同じような境遇の仲間と交わす笑顔は束の間の夢。彼女たちは罪を犯した。でも…罪とは、何なのか?「加害者になるしかない命」もまた、立派な被害者なのだ。
春名 風花
声優・女優
社会構造のひずみは、最も立場の弱いものの上に現れる。日本でもイランでも。
この作品は、どこにでも社会の歪みにより深い裂け目が広がっていること。
そして、その裂け目を繕おうと努力している人たちがいることを伝えてくれる。
この作品は、どこにでも社会の歪みにより深い裂け目が広がっていること。
そして、その裂け目を繕おうと努力している人たちがいることを伝えてくれる。
杉山 春
ルポライター
更生・矯正が必要なのは少女たちなのか?
それが必要なのは、彼女らを「正」ではない行為に追いやった環境や社会ではないのか。
傷つき道を失った少女たちに、大人がしてやれるのは「あなたは悪くない。悪かったのはあなたではなかった」と、繰り返し語りかけてあげることでしかない。日本から7500km離れたイランで撮られたこのドキュメンタリーを通じて、改めてそのことを痛感した。
傷つき道を失った少女たちに、大人がしてやれるのは「あなたは悪くない。悪かったのはあなたではなかった」と、繰り返し語りかけてあげることでしかない。日本から7500km離れたイランで撮られたこのドキュメンタリーを通じて、改めてそのことを痛感した。
鈴木 大介
文筆業
どうしたら収容所という特殊な場所で、少女たちの人間らしい姿をここまで自然に写せたのだろうか。相当に強固された信頼関係の構築は間違いないだろう。社会や家族から壮絶な裏切りを受け、愛を受けられないまま犯罪に手を染めてしまう。犯罪者として扱われ心から血を流すほどに傷ついている少女たち。そんな少女たちが同じ境遇の仲間たちと愛を与えあい、支え、支えられながら何とか生きようとする、人間本来の弱くて強い姿に何度も涙が溢れた。
白川 優子
NGO看護師
ドキュメンタリー映画の紹介で、「カメラで追った」という言い回しは頻繁に使われる。だが、この映画は「追う」のではなく、カメラがそこに「留まる」ことで、少女たちの心と身体が、どれほどの傷と痛みに満ちているかを映し出す。さらに、そこからこぼれ出る叫びを、オスコウイ監督は留まって受け止めていた。彼女たちの傷跡の「痛々しさ」は、イランから日本への問いかけでもある。
綿井 健陽
映像ジャーナリスト/映画監督
抑圧的な社会でひどい目にあうのは女こども。そして、女でありこどもである少女は一番ひどい目にあう。
けれど、この悲惨な境遇の少女たちの尊厳の輝きはどこから来るのだろう。少女たちには荒みのかけらもない。そして、彼女たちの夜明けのベッドルームにいる、天使のようなカメラの奇跡。
私はいったい何を見たのだ?!
けれど、この悲惨な境遇の少女たちの尊厳の輝きはどこから来るのだろう。少女たちには荒みのかけらもない。そして、彼女たちの夜明けのベッドルームにいる、天使のようなカメラの奇跡。
私はいったい何を見たのだ?!
池田 香代子
翻訳家
少女たちがカメラの前で自身の過去をひとつずつ振り返り、自らの言葉で語り直すこと。
客観し他者を受け入れ、安定を取り戻し、将来に向けてまさに歩み出す奇蹟の瞬間に私たちが疑似としてだが立ち会うこと。証人としての立場を引き受けること。
語り直しが行われ、彼女たちが暗闇から抜け出る姿を見出す安堵。映画の治癒効果。
私たちの役目は「知る」ということと、次に何か「行動」するということ。
社会の歪みや皺寄せは不可視の一カ所に集中する。そして被害は連鎖する。
このような少女たちは遠い異国の話ではなく、私たちのすぐ隣の部屋でも起こっているということも決して忘れてはならない。
客観し他者を受け入れ、安定を取り戻し、将来に向けてまさに歩み出す奇蹟の瞬間に私たちが疑似としてだが立ち会うこと。証人としての立場を引き受けること。
語り直しが行われ、彼女たちが暗闇から抜け出る姿を見出す安堵。映画の治癒効果。
私たちの役目は「知る」ということと、次に何か「行動」するということ。
社会の歪みや皺寄せは不可視の一カ所に集中する。そして被害は連鎖する。
このような少女たちは遠い異国の話ではなく、私たちのすぐ隣の部屋でも起こっているということも決して忘れてはならない。
ヴィヴィアン佐藤
美術家・ドラァグクイーン
私の知らなかったイランが、ここにはあった。けれどもまた、この少女たちの体験は、私の国で少女たちの身に起きていることと、あまりにもよく似ていると思った。イランの少女たちは国営の施設の中で笑顔を取り戻すが、外に出たならどうだろう?そして私の国は、笑顔を取り戻せる場を用意しているのだろうか?
渡辺 一枝
作家
売春、強盗、性的虐待。彼女たちのバイオグラフィーに刻まれた痛みは華奢な身体では抱えきれないほどに鋭く重い。しかし、少女更生施設内には希望も同居している。楽しげに歌って踊って快活に身の上や罪状を話したかと思えば、泣きながら胸のうちを吐露しては無言で背中をさすり合う。異なるバックグラウンドを持った少女たちが"痛み"でつながり、絆を紡いでいく場所。それを皮肉や悲劇と呼ぶ人もいるかもしれない。それでも、私はそこに真のシスターフッドとささやかな希望を見た。
佐々木 ののか
文筆家・ライター
いつからだろう。大きな塀が社会という広く冷たい場所から守っているように見えてきたのは。
「少女は、加害者になる前に被害者だった」そう知るようになったのは、私が女子少年院に講話に行くようになってからだ。少女は過酷な世界で生きている。罪を犯し、収容された更生施設が少女とって、唯一心を許せる居場所。それは国境を越えても変わらない。 少女のかなしい笑顔とその言葉が胸に突き刺さる。
どうか世界中の小さな声が届きますように、そう願わずにはいられない。
「少女は、加害者になる前に被害者だった」そう知るようになったのは、私が女子少年院に講話に行くようになってからだ。少女は過酷な世界で生きている。罪を犯し、収容された更生施設が少女とって、唯一心を許せる居場所。それは国境を越えても変わらない。 少女のかなしい笑顔とその言葉が胸に突き刺さる。
どうか世界中の小さな声が届きますように、そう願わずにはいられない。
中村 すえこ
作家・映画監督
なぜこんなにも心揺さぶられるのだろう。重く閉ざされた施設の中の少女たちの破顔。あどけない表情の少女たちがさらりと告白する重い罪や痛ましい家庭環境。そして秩序や建前を繰り返し、少女たちの心の叫びに応え切れない大人たち。映像と肉声とが突きつけるありとあらゆるギャップに心が締めつけられる。この映画が遠い国の物語だと言い切れる人はいまの日本にはいまい。見えない世界、あるいは見たくない現実を少女たちとの誠実な対話を基に可視化した監督の手腕と覚悟にただただ圧倒される。
内山 拓
NHKディレクター
貧困、暴力、女性差別。あからさまな困難があり、罪を犯した少女たちが戻っていく社会は過酷である。しかし、貧困や差別が周到に隠されている社会にはない、受け入れの眼差しを感じたこともまた事実だ。
女より男の命の方が重いとでも言うのか?
仕方ないと首をふるのか、怒るなと抑圧するのか。
彼女たちの側に立ち、ともに声を上げるのか。
女より男の命の方が重いとでも言うのか?
仕方ないと首をふるのか、怒るなと抑圧するのか。
彼女たちの側に立ち、ともに声を上げるのか。
小川 たまか
ライター